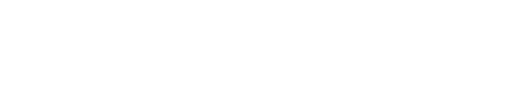『赤城と比叡』
黒井緑 白泉社 \780+税
(2015年5月29日発売)
『赤城と比叡』は、軍艦・海戦を描いた短編集である。
同じジャンルつながりか、『沈黙の艦隊』などのかわぐちかいじがオビで大絶賛している。
「こだわって描き上げた軍艦への愛。これこそマンガの力。そして面白さ」
「舷側の鋲 甲板の錨の鎖/それら一つ一つにこだわって描き上げた軍艦への愛。絵も、物語も、とことん細部に執着する。神は細部に宿り、リアリズムとなって立ち上がる。これこそマンガの力。そして面白さ」
本書のすばらしさを伝えるには、かわぐちかいじの絶賛を引用するだけで充分なのだが、それだけでは不親切なので、内容について言及しておこう。
「赤城と比叡」と聞くと、少し軍艦に詳しい人であれば、太平洋戦争時に活躍した、航空母艦「赤城」と戦艦「比叡」の物語を想像するだろう。
しかし、表題作の『赤城と比叡』で描かれているのは、日清戦争時の黄海海戦での砲艦「赤城」とコルベット艦「比叡」の奮戦ぶりである。
本書では、日清戦争から第二次世界大戦の間の東西の海戦・作戦が取りあげられている。そこで主人公となるのは、戦艦や航空母艦といった主力艦ではなく、潜水艦や駆逐艦、砲艦といった小艦艇である。
小艦艇に焦点をあてて物語を作りあげているのは、サブマリナー(潜水艦乗り)であったという著者・黒井緑の経歴ゆえであろうか。
そして、小艦艇たちの活躍の舞台となる海戦も――「赤城と比叡」の黄海海戦を除けば――あまり知られていないものだ(第一次世界大戦中に、連合国側の輸送船の護衛任務にあたるため、欧州に派遣された日本海軍の「第二特務艦隊」のエピソードを取りあげるなど、じつにシブい選択だ)。
そして、知名度のない海戦・作戦であっても、そこには大海戦に負けないドラマがある。
たとえば、「いさましいちびの土蛍(土蛍にグロウウォーム)」は、攻撃力・防御力ではるかに及ばないドイツの巡洋艦に対し、「見敵必戦」の英海軍の伝統精神から闘いを挑んだ英駆逐艦の物語である。
巡洋艦アドミラル・ヒッパーに対峙して、駆逐艦グロウウォーム艦長・ループ少佐は「あの測距儀にしろ、八インチ砲にしろ、最新式なんだろうが、いずれ過去のものとなる、だが、古いものは古くならないんだよ」と呟き、砲撃でも雷撃でもない戦法を選ぶ……。
現代の海戦はレーダーなどの電子兵器により戦われるため「敵」は見えない状態での戦闘となる。
そうしたゲームのような戦闘では生まれづらいドラマ性にこだわるがゆえに、黒井緑は相手方を視認して戦う海戦にこだわっているのだろう。
本書に登場する艦艇は、煙突から黒々と煙を吐いて航行する(煙の擬音としては「モクモク」が一般的だろうが、黒井は「モモモ」なる特徴的な擬音を用いている)。
そして、登場人物たちは、狭い艦橋で潮風に打たれながら、敵影を探索する。
このような人間臭い海戦が描けるのは、レーダーなどの電子兵器が長足の進歩を遂げるまで(1942年くらいまで)になってくるのではないかと思う(55頁の独潜水艦・Uボートの装備の変遷を描いたおまけカットが象徴的である。「大西洋の狼」として大活躍したUボートも、レーダーの発達後は、水中への潜航がメインとなって戦果を挙げる機会がほぼ失われてしまったのだ)。
本書の巻末には「All aboard!」と題した、描きおろしとしてこれから描かれる作品の予告マンガが6本掲載されているのだが、このなかで興味深いのは軍艦VS対艦ミサイルの闘いを描いた「死の翼 スティックス」である。
人間臭いドラマを盛り上げにくいであろう、軍艦とミサイルとの戦いを黒井緑がどのように描くのか興味の引かれるところである。
<文・廣澤吉泰>
ミステリマンガ研究家。「ミステリマガジン」(早川書房)にてミステリコミック評担当(隔月)。『本格ミステリベスト10』(原書房)にてミステリコミックの年間レビューを担当。最近では『名探偵コナンMOOK 探偵少女』(小学館)にコラムを執筆。