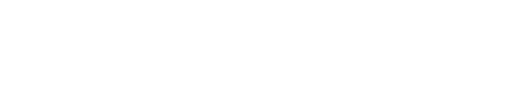『兄帰る』
近藤ようこ 小学館 ¥933+税
8月30日は国際失踪者デー。失踪者についての意識を高めるためにアムネスティ・インターナショナル、赤十字国際委員会などが制定した。
我が国でも拉致問題への関心が風化しかかっているが、関係者にとって時間は残酷だ。拉致被害者の肉親たちが老いていく姿を見るにつけ、早期の進展を願ってやまない。
この国際失踪者デーは、紛争や事故に巻きこまれて、あるいは国家権力そのものによって行方知れずとなった、いわゆる強制的失踪者への関心を高めるために制定されたものだが、みずからの意志で家族や友人の前から姿を消してしまう人も少なくない。
いったい彼らに何が起こったのか……。残された者は断片的な情報を拾い集めながら、思いをはせることになる。
近藤ようこの『兄帰る』は、3年前に置き手紙1枚を残して婚約者の真樹子や家族の前から姿を消した野田功一が、交通事故で帰らぬ人になるシーンから始まる。
遺品を整理すると、見知らぬ人々といっしょに収まっている功一の写真や、書きかけの手紙が出てきた。真樹子と功一の家族は、彼がこの3年間を過ごしたゆかりの場所をたどり始める。
市井の人々が紡ぐドラマを、唯一無二の視点で描いてきたベテラン・近藤ようこだけに、功一が「国家を揺るがす重大な秘密がを握っていた!」だとか「とんでもない二面性を備えていた!」といった大仰な展開が待ち受けるわけではない。
ただ、ひたすらに「人間とは決して一面だけではとらえられない」ということを、真樹子や野田家の人々を通して伝えてくれるのだ。
「しあわせ、ふしあわせの収支は、その人の心の中でつけるしかないのだ」という近藤自身の後書きが、深い余韻を与えてくれる。
<文・奈良崎コロスケ>
マンガ、映画、バクチの3本立てで糊口をしのぐライター。話題の映画『ピクセル』の劇場用パンフレットに参加することになり、80年代カルチャーを復習中。