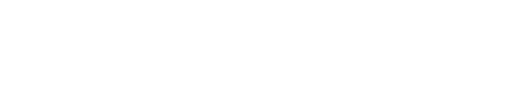りくの鋭い感受性によるある行動をきっかけに、りくはママが敬遠していた関西の親戚の家にしばらく預けられることになってしまう。ショックを受けるものの、自分を遠ざける母への意地でりくは関西へ向かう。

逢沢家ではやっかいもの扱いだった鳥だが、関西の大おば宅では名前を何にするかで大白熱のやりとりに発展!
りくが預けられた関西の家は、大おば夫妻と高校生の次男、そして長男一家が日常的に出入りするにぎやかな大家族だ。
大おばをはじめ関西の人々はりくの戸惑いにおかまいなしにぐいぐいコミュニケーションをとってくるのだが、その饒舌な会話のテンポがよく、読んでいて思わず笑ってしまうおもしろさだ。関西弁嫌いのりくとの温度差もおかしく、この会話部分が間違いなく本作の大きな魅力のひとつになっている。
「どうしてここの人たちはものごとの価値の決め方が『おもしろい』か『おもしろくない』なんだろう」とりくは戸惑うが、ベタなユーモアを織りこみつつ、いろんな年代の人々が交わす怒濤の会話は、馬鹿馬鹿しいようで、じつは高度な経験と訓練を経たコミュニケーション術なのである。

りくを慕う幼児・時ちゃんに、すげない態度のりく。だが、このとき放った言葉がのちに、意外な形で反復されることに。
作中では、東京と関西の生活が対比的に描かれ、関東在住の私からすると、「ちょっとずるくないですか?」と言いたくなるくらい、関西の人々は魅力的だ。
東京の人々は総じて「美少女」のりくの「美」に惑わされて本質を見落としがちだが、関西の人々の多くは、りくの「美」ではなく「少女」(=子ども)の部分に重点をおいて、りくを人としてクールに見守りつつ温かく接しているように思える。なんだろう、この洗練されたまっとうな「子ども扱い」。おそるべし、作中の関西のひとびとの(年齢を問わない)「大人」っぷり。
その大人な部分は、核家族化が進んでコミュニケーションの質が変わった現代には失われがちな美徳だけれど、子どもを、ひとを育てるって、つまり、そういう知恵が大事なんだよなあと感じさせてくれるのだ。
物語が進むにつれ、りくが東京から連れてきた鳥や、りくの学校の早退、そしてりくの涙も、最初とまったく違う意味をもつようになっていく。
あからさまな感動の強要には「泣かされてたまるか」とかまえてしまうタイプの読者(私もそのひとりだ)も、さりげなくも周到にはられた伏線と、何重にも胸に響くセリフ、そしてとぼけた演出に、笑いながらも涙腺を刺激されてしまうだろう。
そう、本作は、鋭い指摘にドキリとしつつ、おおいに笑って泣いてしまう、現代の傑作寓話なのである。
『逢沢りく』著者のほしよりこ先生から、コメントをいただきました!
<文・川原和子>
マンガエッセイスト。幼稚園教諭、アニメ制作会社等を経て独立。著書に『人生の大切なことはおおむね、マンガがおしえてくれた』(NTT出版)。NTT出版Webで新連載準備中。連載 おすすめマンガ時評『此れ読まずにナニを読む?』(NTT出版Web内)。
「マンガラブー」