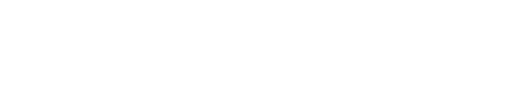近年は序盤において、いわゆる「設定」的な情報をつめこんだ作品が多いなか、まさしく少年とともに一歩一歩と踏みしめるように探っていく感覚が新鮮だ。
まさしくそれは、真っ白なキャンバスにひとつひとつ筆を置き、色を乗せていくような感覚。序盤の物語が、雪に覆われた純白の世界だったことは、その意味で非常に象徴的と言えるだろう。
そして「それ」は、少年と別れて動き始めるわけだが、その歩みは凄絶のひと言。人間のかたちをした何かが、幾度もの「死」を繰り返しながら成長していく様は、見ていて痛々しいと言うほかない。

本作のタイトルにもあるように、文字どおりに不滅である「それ」。しかし、そこにある痛みの描写はすさまじい。
だが、そんな辛く苦しい描写から一転し、穏やかな生活が描かれるある集落。静寂と死にすべてが飲みこまれてしまう序盤とはガラリと変わり、ある程度の人々が暮らすその集落は、平和な空気すら感じられた。
しかし、その平穏は極めて危うい均衡のもとに成り立っていることがやがてわかる。それが集約されるのが、いまだ残る「生贄」の風習。
その儀式が進むなかで、まだ生きたいと願う幼い少女・マーチと「それ」が遭遇する──。そこで起こる衝撃のできごとをここで語ることはさし控えておくが、この出会いが2人に、あるいはこの小さな集落の社会に何をもたらすのか、あらゆることに興味は尽きない。

「生」のエネルギーに満ちあふれながら、その未来を絶たれようとする少女・マーチと、決して死なないながらも、どこか生気に欠ける「それ」。対照的な2人の出逢いは、いかなる運命をもたらすのか?
今後の展開については、まだ多くの部分が謎に包まれているため、何が起こるのかはまったく予想つかないわけだが、じっくりと描かれるであろう物語に身を委ねることとしたい。
たしかに「世界観」は謎だらけだが、「作品観」は驚くほど明確なのだから。そして触れたものによって姿を変える「それ」と同様に、この作品自体もまた、触れる人によって様々な読み方ができるものであることにも期待したい。

<文・大黒秀一>
主に「東映ヒーローMAX」などで特撮・エンタメ周辺記事を執筆中。過剰で過激な作風を好み、「大人の鑑賞に耐えうる」という言葉と観点を何よりも憎む。