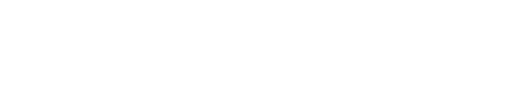『ルーヴルの亡霊たち』
エンキ・ビラル 小学館集英社プロダクション \3,000+税
(2014年10月29日発売)
“所蔵する作品やコレクション、もしくは美術館自体を題材として、ひとつの物語を「マンガ」で語ってほしい。”
パリのルーヴル美術館からの呼びかけに、著名な漫画家たちがそれぞれ独自のアイデアで答えた――。
この冒険的なプロジェクトの成果は、これまでに全部で12冊の書籍としてまとめられている。谷口ジローによる『千年の翼、百年の夢』(フランス語版タイトルは『Les gardiens du Louvre』。日本語版は2015年1月末刊行予定)がその最新作。
荒木飛呂彦もかつてこのプロジェクトに参加していて、『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』はすでに日本でも出版されている。
その他にも、マルク=アントワーヌ・マチュー『レヴォリュ美術館の地下 -ルーヴル美術館BDプロジェクト』と『氷河期 -ルーヴル美術館BDプロジェクト』が日本語に翻訳されて、読めるようになっていた。
今回、日本語で読めるこのコレクションにあらたな1冊が付け加えられた。
ユーゴスラビア出身のフランス人作家エンキ・ビラルが描く『ルーヴルの亡霊たち』だ。日本人マンガ家だけでなく、世界中のクリエイターに影響を与えた作家として、しばしばメビウスともに名が挙げられるビラルは、鉛筆デッサンの上に絵の具を重ね、ときにはさらに鉛筆の線を加えるその独自の画風で知られる。
本作では、ルーブルに収められている絵画や彫刻作品、あるいは部屋そのものに取り憑いた「亡霊」たちが描かれる。
ビラルの想像力によって具体的に名前とその生涯を与えられた彼らは、作品を描いた画家自身や、その中に描かれたモデルではなくて、作品と同じ時代を生き、その作品と関係のあるなんらかの非業の死をとげた人物たちだ。
「亡霊」たちは作品に直接的な恨みがあるわけではない。それはただ執着の拠り所として選ばれているだけだ。ビラル独特の画風で描かれた「亡霊」たちが、ルーブルの作品を写した写真の上に浮き上がり、いかにも何かを伝えたそうだけれど、その何かは絵からも文字からも、はっきりとは示されない。だからこそ、画面には亡霊たちの執着という情念だけが残され、不気味に漂う。
写真と絵を組み合わせ、別のページにテキストが書かれたこの作品は、もしかしたら「マンガ」じゃないのかもしれない。
しかしながら、イメージとテキストでかつてない情感を伝えるこの形式は、これまでとは違ったマンガのあらたな可能性を秘めているようにも感じられ、ビラルの才能をあらためて確認させるものであることはまちがいない。
<文・野田謙介>
マンガ研究者、翻訳者。雑誌「Pen」の特集「世界のコミック大研究。」(阪急コミュニケーションズ、2007年、No.204)の企画・構成を手がける。訳書に、ティエリ・グルンステン『マンガのシステム――コマはなぜ物語になるのか』(青土社、2009年)、エマニュエル・ギベール『アランの戦争――アラン・イングラム・コープの回想録』(国書刊行会、2011年)。