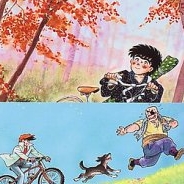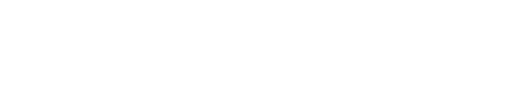『ジパング少年』第1巻
いわしげ孝 小学館 \485+税
4月3日はペルー・日本友好の日だ。日本からペルーへの最初の移民790人を乗せた佐倉丸が、1899年にカジャオ港に到着した日を記念している。
以降、日本からペルーへの集団移住が始まるが、文化や習慣の違い、風土病などの影響で、その道のりは困難を極めた。現地社会との軋轢など紆余曲折を経ながらも、移民者たちは日系社会を形成していった。
そして1990年には、日系のアルベルト・フジモリが大統領に選出され、日系社会が大きくクローズアップされた。
そんなペルーの日系社会が登場する作品といえば、いわしげ孝『ジパング少年(ボーイ)』である。
主人公・柴田ハルは、日本の高校に通う普通の学生だったが、いきすぎた管理教育に疑問を感じ、高校の教師たちとことあるごとに衝突を繰り返すようになる。
掲載誌「ビッグコミックスピリッツ」で連載が開始された1988年当時は、事実、服装や髪型の強要や厳重な持ち物検査、校則の徹底や体罰といった「管理教育」が全国的に問題となっていた。 1990年、神戸高塚高校では登校時間を取り締まるために、校門を強制的に閉鎖、女子生徒が校門にはさまれて圧死する痛ましい事件も起きた。この事件も、作中では印象的なエピソードとして挿入される。
やがて日本の学校を飛び出した柴田ハルは、ペルーからの帰国子女・森ととらら友人とともにペルーに渡り、ガリンペイロ(金堀り人)で資金を貯めつつ、インカ帝国の遺跡を探すようになっていく。
先が予測できない物語と、ペルー社会のディテールに圧倒されることは必至である。
わけてもインカの幻の遺跡・ビルカバンバをめぐる終盤の物語は、息をつかせぬ展開の連続だ。
ガリンペイロとなった柴田ハルらはある事件を契機に日系社会と交わるようになるが、当時問題となっていた武装ゲリラや、ペルーにおける日系社会の複雑な立ち位置、日系人大統領の影響なども描かれる。
1980年代後半から90年代初頭にかけて、日本は未曾有の好景気に浮かれていた。そのバブル社会とアマゾン川流域の社会の対比も、さまざまな問題を浮き彫りにする。
経済の絶頂期にその社会を疑問視し、人間らしさや自分の望む生き方を模索する姿は、当時の読者に大きな影響を与えた。かといって主人公の柴田ハルは卓越した存在ではなく、ひたすら等身大のティーン・エイジャーとして悩んで悩んで悩み抜く。その「青臭さ」こそが、いわしげ孝の真骨頂であり、最大のチャームポイントである。
日本にはジャック・ケルアックは生まれなかったが、いわしげ孝がいたのだ。
<文・加山竜司>
『このマンガがすごい!』本誌や当サイトでのマンガ家インタビュー(オトコ編)を担当しています。
Twitter:@1976Kayama