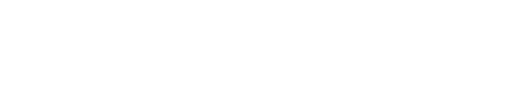美しくも切なく、どこか懐かしさを感じさせる新感覚ファンタジー『クジラの子らは砂上に歌う』。読者を引き込む作品の魅力はどのようにして生まれるのか? 梅田先生の漫画家としてのルーツとともにその秘密を解き明かす!
さらにさらに、気になる今後の展開についても直撃!!
記録係チャクロの存在があるからこそ生まれる、歴史懐古的な独特の世界観

インタビュー時に使用したホワイトボード。…よく見ると梅田先生のカワイイ落書きが…
――『クジラの子らは砂上に歌う』の主人公で記録係のチャクロは「ハイパーグラフィア(過書の病)」という、要は記録フェチという設定で、物語全体の構造としては、すべてが終わった未来から第三者がチャクロの記録を通して、泥クジラの人々が辿った歴史を懐古するようなスタイルが取られています。
それが独特の感傷的な世界観に繋がっていますよね。

各巻の巻末にある「あとがきまんが」には、本作の誕生秘話が!? チャクロの膨大な記録を読み解くのは骨が折れそう……。
梅田 私、もともとヘンリー・ダーガーの『非現実の王国で』[注1]にすごく影響を受けてて。
あれって孤独な老人が、子どもの頃から一生をかけて自分のためだけの空想を書き綴っていたものが、お年寄りになって施設に入るためにアパートを出ることになって初めて、管理人さんによって発見されたんですね。他人といっさい交流がなかった彼にとっては、その架空の世界が人生そのもので、本来なら誰にも知られず彼の死とともに消えていたものが、たまたま発見されて私たちが知るものになったという。
作品自体もすごいけど、ヘンリー・ダーガーさん自身の人生とか、その記録のたどった数奇な運命みたいなものにもグッとくるものがあって。
――ヘンリー・ダーガーとは、納得ですね。作中では「記録の不思議」を読者に説くようなモノローグも繰り返し登場しますが。
梅田 誰が作ったかわからなくて、なんか残っちゃったようなものが好きで。古い民話とか、別に作家じゃない人が語り継いだ伝承みたいな匿名性が高くて、なんか残ってるものに魅力を感じるんです。話の作りかたみたいなものって古今東西、パターンが決まってるらしくて。
たとえば、浦島太郎みたいにどっか異世界に行って帰ってくるみたいな話が、なぜか世界各地に残ってたりしておもしろいなって。一時期、昔話論みたいなものを読んだりもしてたんです。
――たしかに、ウラジーミル・プロップ[注2]みたいな、昔話の類型にのっとったようなスタンダード感も『クジラ~』にはありますよね。
梅田 まさに、ウラジーミル・プロップも読みました(笑)。最初は技法書みたいなのを読んで作るのは抵抗あったんですけど、実際に読んでみたらすごくおもしろい! それに、似た話がたくさん残ってるってことは、やっぱりそれが人をいちばん引き込むパターンだからかなと思って。
好きなものは出せばいいやって。
――『クジラ~』にはお葬式にあたる「砂葬」とか、年に一度みんなで砂をかけ合う「スナモドリ」といった儀式があったり、民俗学的な要素も盛り込まれていますが。

悲しくも美しい砂葬のシーン。花で埋め尽くされた棺に入り死者は砂の海へ帰り、その魂はクジラの民を守るという。
梅田 民俗学も好きなんですね。『クジラ~』はどこでもない世界のお話ですけど、読むのは日本人なので、日本人が共感しやすい設定にしたいなと思って。
私のなかでは「スナモドリ」はじつはお盆の灯籠流しで、バッタが飛ぶ「飛蝗(ひこう)現象」を見るシーンは花火大会(笑)。はっきりそれとはわからなくても、なんとなく読んだ人が郷愁を感じて、泥クジラの世界に入り込みやすくなればいいなと思って。

砂をかけ合い、砂に溶けた故人の魂を迎える「スナモドリ」がお盆とはなるほど。敵襲撃を翌日にひかえ、砂を見つめるみなの表情はさまざま。