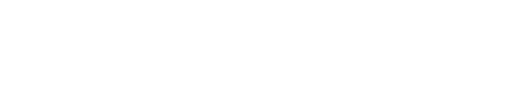ひと言でいうと本作は「サブカル女子×リア充イケメン」の物語。だが、この2人を対極的にカリカチュアとして描くのではない姿勢に、魅力と説得力を感じる。
第1巻で示されているのは「人が親しくなるのに好みが合う、合わないは関係ないのでは?」ということ。そして、「サブカル系」に限らず人をくくることが(ときには自ら)、自分を不自由にしているのではないかということだ。

SNSで知り合った文化系おじさんがウンチクをしゃべりまくる姿に、リンダはこれは本当のコミュニケーションではないと気づく。
「サブカル系」がハリウッド超大作や泣ける恋愛映画のような“ドメジャー”に背を向けるのは、それらを低俗と見下しているからではなく、単に好みの問題。
だけど、“みんな”が知らないマニアックな知識を備えていることに多かれ少なかれ優越感を持っているのは否めない……リンダがカウンターをはさんでエドガーと話すなかで、やっかいな自意識によって自分を閉ざしていたことに気づいていく過程はじつに読みごたえがある。
リンダはそもそもは素直で他人をカテゴライズしない。だからこそ、エドガーは好みは合わなくとも彼女と話すことが楽しいのだろう。
「○○系」「○○男子」「○○女子」といった言葉をただのネタとして使う分にはいいけれど、ときに他人をざっくり判断しすぎていないか。それは自分の世界を狭めることにもならないだろうか。

日々エドガーのバイト先のバーに通ううちに2人は親しくなって……。リンダの好きなドランの映画を観たエドガーの感想が正直すぎてすがすがしい!
リンダはエドガーと親しくなったことにより、大きく変化しつつある。そこに「恋」というキーワードが浮上し、これからどんな命題が登場してくるのか楽しみである。

<文・粟生こずえ>
雑食系編集者&ライター。高円寺「円盤」にて読書推進トークイベント「四度の飯と本が好き」不定期開催中。
ブログ「ド少女文庫」