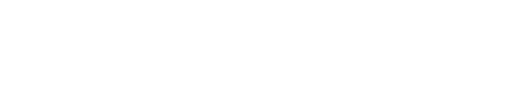当初、『ヒメアノール』の安藤さんを彷彿させるダメダメ中年男の恋愛迷走劇か――と思って読んでいたらば、想像を絶する展開にポカーン!
すぐに店長の夢or妄想オチ? と思いあたるも、倉内視点では店長が消えたことになってるし。

社会不適応男の妄想オチかと思いきや…。いかにも意味深げで、その実なんにも言ってない会話がシュールすぎます!
「他者」に触れられた瞬間、「世界」が変わるという設定といい、
「なんにもないんだよ マジで 死んでるようで死んでいない」
「この状態に意味とか求めない方がいいぜ?」
「オレは自分が誰か知りたいな」
「人間には他人の目が必要なんだぜ?」
「これが正気でいるコツだ」
といった禅問答のような会話といい、哲学的なメタファーかなんか? と思いながらも、ワケがわからず読み進めると、彼らの前に「森」が登場。そこで出会ったもうひとりを含めた仲間の呼び名が「モウソウ」と「正気」――と来た日にゃあ、誰もが心理学かよ! とツッコまずにいられない。

いちいち真剣に受け止めて読んでいたら頭がイカれてきそう……。どこまでがギャグでどこまでが本気なのか? 作者の真意がナゾだからこそ引きこまれる!
この「くだらなくも意味ありげ」なメタファーのくどいまでの乱用、ギャグと不条理が混在する世界観は、松本人志の映画『しんぼる』をおのずと喚起させる。
一方で、ハンプティ・ダンプティのような道化的ルックスでシリアスな禅問答を繰り返す彼らは、まさに『不思議の国のアリス』のハンプティ・ダンプティそのものでもある。
ハンプティ・ダンプティは俗に「一度壊れると容易には元に戻らないもの」の比喩とされ、さらにポール・オースターの小説『シティ・オブ・グラス』のなかでは、「人間の状況のもっとも純粋な体現者」と分析されていたことを思えば、この『グレクシス』の物語が意味するものは――なあんて、あれこれ深読みしたくなってしまう。
考えてみれば、古谷実は『ヒミズ』以降、「肥大した自意識」や「ディスコミュニケーションな現実」に悩む主人公を軸に、一貫して「世界の危うさ」を執拗なまでに描き続けてきた。
そういう意味では、現時点では異世界モノ!? と思える本作もまた、いじめや犯罪の匂いこそないが、その系譜に位置する作品であることは間違いない。
とにかく、現時点では「わけがわからん」ながらも「想像もつかない“何か”が起こり」まくってることはたしかで。世紀の名作か、あるいは迷作か!? どっちに転ぶにしても、いまだかつてない「怪作」となる手ごたえビンビン。
マンガ読みならずとも必読の本年度最重要作品だ。
<文・井口啓子>
ライター。月刊「ミーツリージョナル」(京阪神エルマガジン社)にて「おんな漫遊記」連載中。「音楽マンガガイドブック」(DU BOOKS)寄稿、リトルマガジン「上村一夫 愛の世界」編集発行。
Twitter:@superpop69