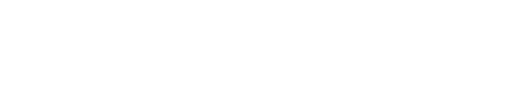『惡の華』で描いた思春期
――作中の風景ですが、「上州のからっ風」といわれるような、群馬独特の荒涼とした感じが印象的です。

数年ぶりに故郷に戻る春日。その心境もあってか、風景はより寂しさをかもしだす。
押見 ありがとうございます。そこは出そうとしました。実家に帰るときに、だんだんと風景がトゲトゲしてくる感じ、今でも感じるんですよね。地元に住んでいる人は、すごく郷土愛が強いんです。テレビを見ていて群馬のことが写ると「おっ」となるから、僕も強いほうだとは思うんですけど。ただ、帰るとちょっとやられてしまう。愛憎入り乱れるというか、不思議な感覚です。
――まさに「ふるさとは遠きにありて思ふもの」[注3]ですね。
押見 今、地元に住んでいる中学生から感想とかもらうと「わかる、わかる」みたいな感じになります。「時代が変わっても、今でもそういう中学生がいるんだな」と、うれしかったですけどね。
――高校を卒業して上京するときは、やはり感慨深かったですか?
押見 どうでしょうねぇ。これ以上地元にいたら死ぬか殺すかしていたな、と思ってました(笑)。けっこう、限界ギリギリのところだったので、「やっと出てこられた」みたいな気持ちでしたよ。

地元への想いは、一言では語れない複雑なものだという。
――そのへんの感覚は、思春期のころには割と共通して持っていたりしますよね。勉強が嫌いなわけじゃない、友だちも嫌いじゃない、でも学校は息苦しい。学校自体が嫌いなわけではない。
押見 ああ、そうですね。ちゃんと学校行ってましたからね。友だちもそれなりにいたし。
――なのに、あの息苦しさはなんだろう?と。同調圧力なんて言い方もありますが。
押見 ありますねぇ。いまだになんだったんだろう、とは思います。
――『桐島、部活やめるってよ』[注4]はそういう雰囲気がありますね。
押見 すごくおもしろかったんですけど、なんか複雑な気持ちになりました。「あのなかにいるか?」と、自分はあのなかの誰でもなかった。だから共感はしなかったというか、ちょっと違う立ち位置にいたのかな。
――『惡の華』のテーマは「思春期を抜け出るまで」とのことでした。ただ、思春期はいつ終わるのか? 区切りの判断は難しいところです。そうすると、どこまでも連載を続けることもできたのでは?
押見 もう少し続ける案も、なきにしもあらずだったんですよね。それこそ大学生編、社会人編みたいに。

妄想のなか、一瞬描かれた社会人の春日と常磐。こんな『惡の華』もあったかもしれない!?
――終わらせる決断は、どこでしました?
押見 スッパリと「ここで思春期が終わりました」「成長しました」というふうには終われないと思っていました。ちゃんと必然的に描こうとすると、そういったラストを描くと嘘になってしまう。なんとなくケリが着いた一区切りまで描こう、と。
――その区切りとして、常盤さんに告白した時点で「終わりますね、これ」と。
押見 常盤さんに告白した時点で、今作のテーマ的には終わったと思いました。「今の自分のところまできたので終わった」というのが近いかもしれない。そこからも発展して色々とあるんですけど、「あとはこれが続くんだよ」っていう感じで、僕は現在までそれが続いている。もちろん、これから何があるかわからないけど、それは別の話になりますからね。
――思春期とは別の話になる。
押見 おそらく思春期の終わりって、スパッと区切れるものじゃなくて、グラデーションのように変わっていくんじゃないでしょうか。軟着陸していくような感じで。あとから振り返ったときに、「あそこが“終わりの始まり”だったんだな」と思う。そういうのが生々しい感じになるんじゃないかな。
――その始点の位置まで描いた、ということですね。
押見 そうです、はい。
――ただ、結論めいた内容ではないというか、「こうあるべき」という話ではありませんでした。
押見 そうですね、説教臭いことをやるつもりはないので。確かに青春で、思春期で、成長物語ではあるんですけど、「こういうふうに成長すべきだ」みたいなことは思わないんです。自分が成功例というわけでもないんで(笑)。
――結果的に、ご自身の作品では最長期間の連載になりました。

押見 ちょうどいいところで終われたなぁ、と思います。
- 注3 室生犀星『 小景異情』。
- 注4 朝井リョウ原作の同名小説の映画化作品(監督吉田大八)。男子バレーボール部のキャプ テンでクラスの中心的人物である桐島が、突如として部活をやめたことを契機として、周 囲の同級生たちに変化が訪れる物語。サブカル界隈では公開当初から激賞された。第36 回日本アカデミー賞では、最優秀作品賞と最優秀監督賞を受賞。。